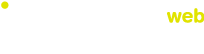インフォメーション 1
手作業の自動化へ挑む。協働ロボット内製プロジェクト/有限会社ウエルダー北沢
愛知・名古屋で塩化ビニル加工を手掛ける㈲ウエルダー北沢。業界共通の課題であった「軟質・枚葉(あらかじめ規定のサイズにカットされたシート)もの」の手作業を自動化するため、専門業者に頼らない協働ロボットの「完全内製」に挑みました。ロボットづくりは未経験。さらに予算も限られている中、100均部材も駆使して生まれたロボットは、生産性向上だけでなく、会社の未来を拓く大きな一歩となりました。今回は挑戦の背景や成果について、㈲ウエルダー北沢の顧問 北沢宗一氏、取締役会長 牧野光昌氏、代表取締役 牧野圭佑氏にお話を伺いました。

有限会社ウエルダー北沢
1962年創業。塩化ビニルやウレタンといった素材を「高周波ウエルダー加工」で溶着・溶断し、文具や包装資材などの製品を手掛ける。ホコリを吸着しやすい製品を扱うことから作業室の入り口にエアーシャワー装置を備えるなど徹底したクオリティ管理を行い、安定した品質を保っている。
手作業の自動化へ挑むプロジェクト
㈲ウエルダー北沢の主力製品のひとつ、塩化ビニル製証券ファイル。手触りや質感に高級感を演出するため、芯材に発泡ウレタンシートを貼り合わせる工程があります。
筆を使ってボンドで貼り付けるこの工程は、乾燥待ちや品質のばらつきを生む手作業に長年依存し、生産性のボトルネックとなっていました。薄く柔らかい「軟質」の「枚葉もの」は、静電気などの影響を受けやすく自動化が極めて難しい。これは業界共通の課題でもありました。
北沢氏がこの難題に挑んだのは、自身の事業継承を進めていた時期。「現場を退くまでの1年間で、会社の未来への布石となる挑戦を」との想いから、プロジェクトが始まりました。

なぜ「協働ロボット」だったのか
実は、初めからロボット導入ありきではありませんでした。当初の構想は「ハンダごての熱でウレタンを仮止めする」というアイデア。しかし人の手では繊細な熱コントロールができず、頓挫してしまいました。このアイデアを実現するため「位置・時間・圧力を正確に制御できるロボット導入」という発想に至ったのです。
ここで選択されたのが、安全柵の不要な「協働ロボット」でした。北沢氏は「工場で他の作業をしながら、人間が確認できる体制が理想でした」と語ります。また、従業員の心理的なハードルを下げることも重要でした。ロボットの動きや配線が見えること、触れれば止まること。「協働ロボット」だからこその安心感が、人と機械が共存する現場には不可欠だったのです。

材料の購入からプログラミング、調整まで。初めてのロボット完全内製
開発は「現場の、現場による、現場のためのモノづくり」をコンセプトに進められました。ロボットシステムの専門業者(SIer)に頼らず、限られた予算で挑む「完全内製」の道です。幸いロボットの販売代理店からのサポートもあり、開発は順調な滑り出しを見せました。ハンダごて付けを担う1台目のロボットはわずか1ヶ月、材料を供給する2台目も3ヶ月ほどで基本的な機能を実装できました。
しかし、本当の戦いはここからでした。どうしても精度が安定しないまま時が経ち、季節は乾燥と低温の冬へ。静電気で薄いウレタンシートがまとわりついて1枚ずつ分離できず、寒さで衝突検知機能が過敏になったサーボモーターは度々停止するなど、開発は困難を極めました。
そんな中、突破口となったのはやはり現場の知恵。一般的なエンドエフェクターだけでは解決不能だったシートの分離問題に対し、試行錯誤の末、自作のグリッパーで「つまむ」という画期的な解決策にたどりつきます。さらに、ロボットのアームを作業場の天井から吊るした輪ゴムで支えてサーボモータの負荷を軽減したり、既存の設備を活用して堅牢な架台として流用したりなど、内製だからこそ可能な柔軟な発想で次々と困難を乗り越えていきました。
さらに4~5ヶ月して、ようやく安定して稼働できる形が完成しました。決して平坦ではなかった道のり。それでも北沢氏は「成果が上がるかは別として、楽しんでやらないと続かないですよ」と笑顔で振り返りました。

生産性向上の、その先へ
完成したロボットは1.25人分の生産性を持ち、手作業は半減。不良品の発生率も人の手と同程度という高い精度を達成しました。現在、運用は牧野光昌氏に引き継がれています。開発時から配線を見える化し、入手しやすい市販品で修理できるよう作られていたことが、スムーズな引き継ぎを可能にしました。
北沢氏はこのプロジェクトを「来るべき次の時代への一歩」と位置づけました。画像認識やAI技術が進化・浸透したとき、「自力で構築した経験があるのとないのとでは、天と地ほどの差が生まれるはず」と未来を見据えます。
生産性向上という直接的なメリットだけでなく、メディア露出によるPR効果や、若い世代への魅力発信、そして会社の未来を照らす挑戦になりました。